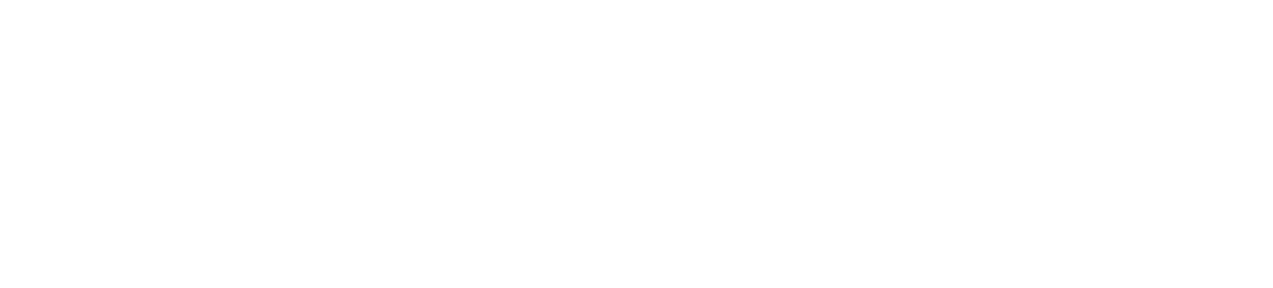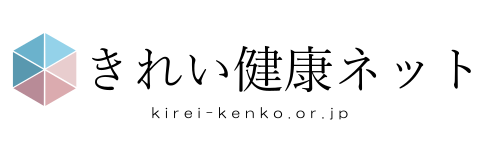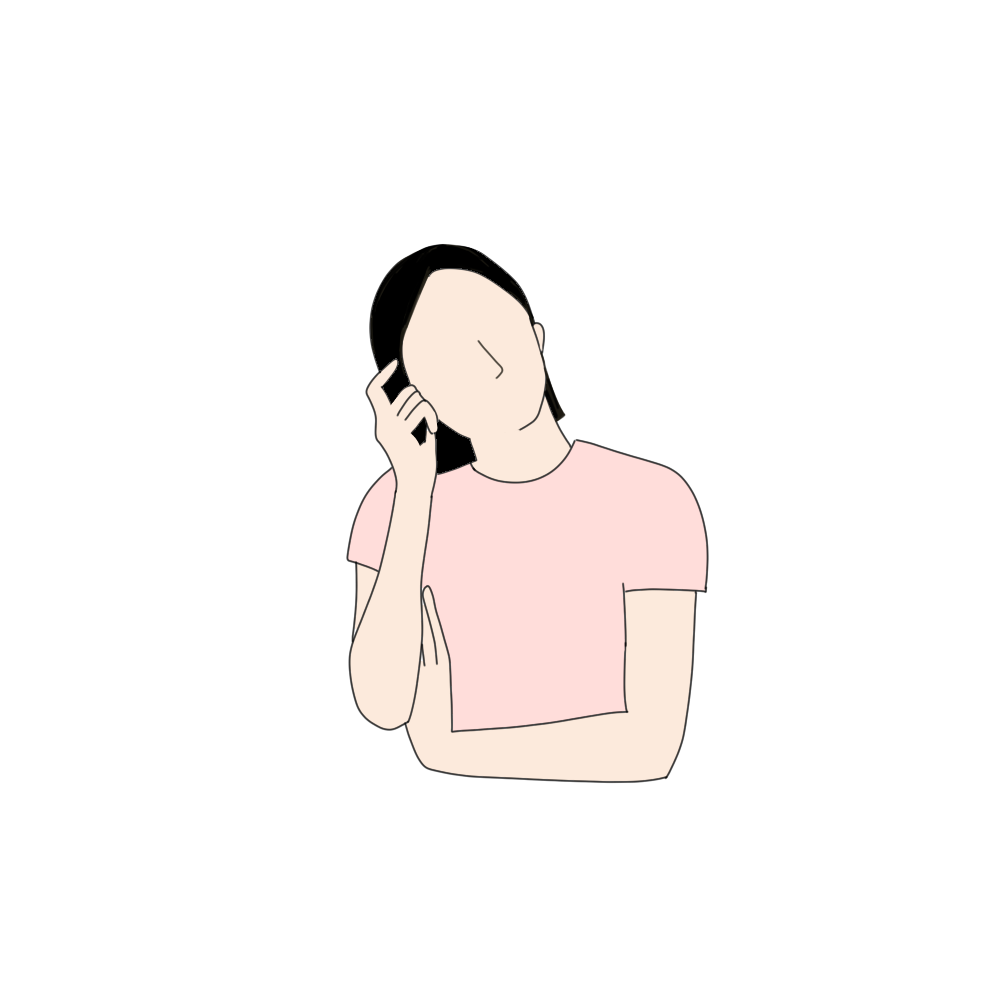胎嚢の大きさ平均と比較ツール
胎嚢の大きさの大きさを平均と比較してグラフに表示します。
胎嚢の大きさ平均と比較ツール
胎嚢の大きさと週数の対応表
胎嚢の大きさと妊娠週数の対応は大まかに以下の通りです。
| 妊娠週数 | およその平均 (mm) |
|---|
胎嚢が平均より大きすぎるまたは小さすぎる場合
特に妊娠初期においては胎嚢の大きさが妊娠の状態や流産の可能性の一つ目の目安となりますが、 平均より大きいまたは小さすぎるからといって妊娠の状態に何かしらの異常があると考えるのは早計です。 グラフに示しているのはあくまでも平均値であり、それを外れていても問題なく生まれてくる赤ちゃんも多くいます。 妊娠初期は特に不安になりやすいのですが、平均は参考程度にとらえてかかりつけの医師の話をよく聞き安静に過ごしましょう。
胎嚢と胎芽は異なりますので注意しましょう
胎嚢と胎芽は異なるものです。胎嚢は赤ちゃんが入っている袋で、胎芽は赤ちゃんそのもののことです。
胎嚢(GS)は胎芽より大きいものです。別の数値を胎嚢の大きさと勘違いして焦らないようにしましょう。
以下超音波検査に出てくる様々な略語です。
● 胎嚢(GS)
胎芽(妊娠10週目までの赤ちゃん)を包む袋のことです。正常な妊娠の場合、妊娠4週から5週頃に子宮内で確認できます。6週から8週以降になると、胎嚢の中に卵黄嚢や心拍の動きが見られるようになります。
● 頭殿長(CRL)
頭からお尻までの長さを示します。妊娠7週から8週にかけて、頭部と胴体の区別がつくようになり、測定できるようになります。妊娠8週から11週の間はCRLに個人差が少ないため、この数値から出産予定日を計算することが可能です。
● 児頭大横径(BPD)
胎児の頭の一番広い横幅の直径のことです。胎児の発育状況を判断する指標となり、妊娠週数の推定や出産予定日の決定にも役立ちます。
● 躯幹前後径(APTD)
腹部の前後方向の幅を表します。胎児の推定体重を算出する際に利用されます。
● 躯幹横径(TTD)
腹部の左右の幅を指します。妊娠20週以降の胎児の成長を見守る目安となります。
● 大腿骨長(FL)
太ももの骨の長さのことをいいます。胎児の成長具合を評価する基準として使われます。