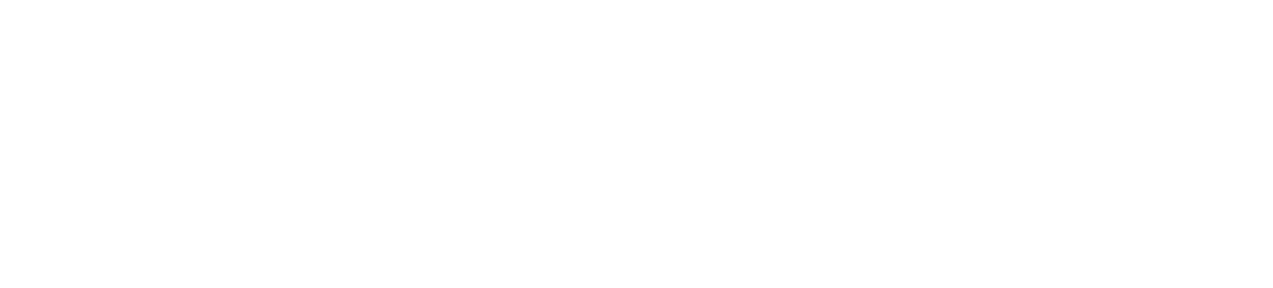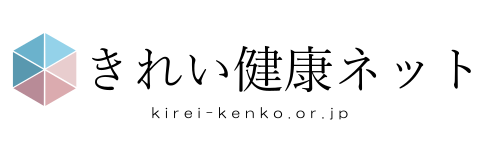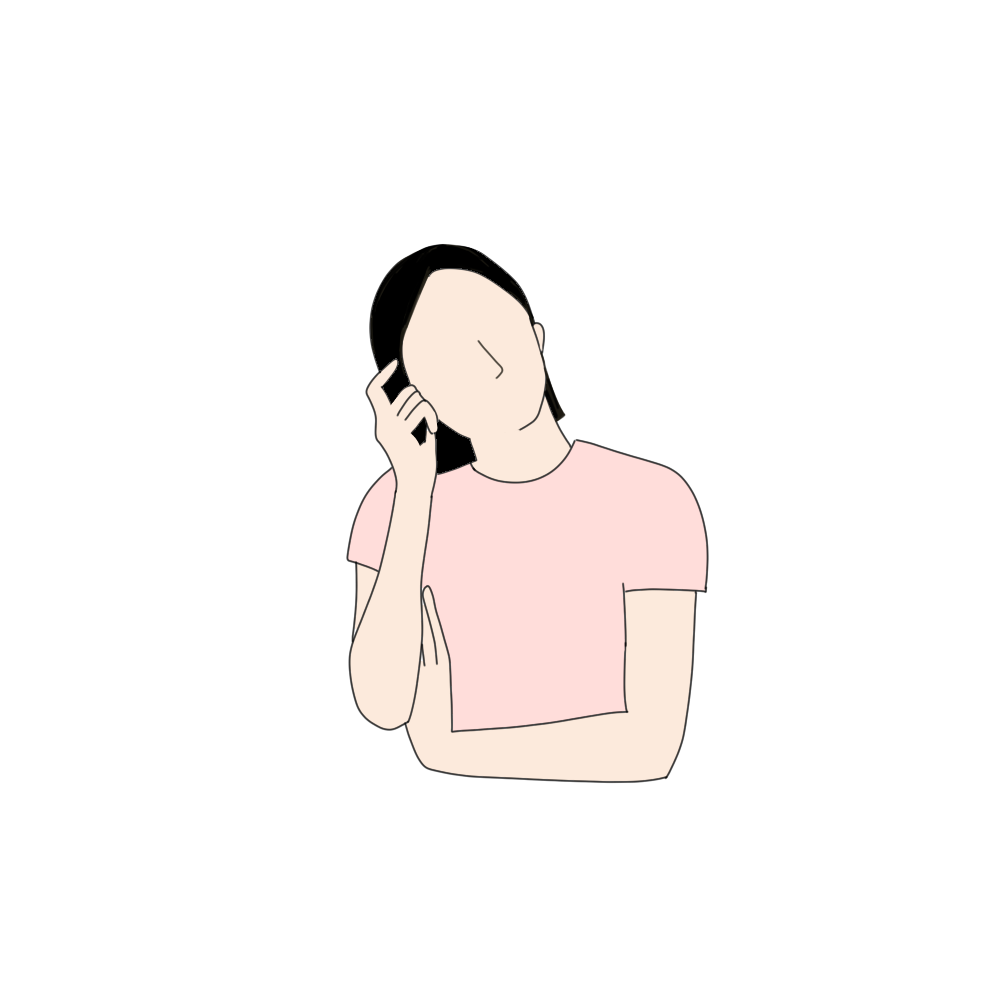産休育休計算ツール
産休育休計算ツールです。出産予定日を起点として産休育休の期間、いつまでとれるのかを分かりやすく見られるツールです。
産休育休計算
出産日を選択しない場合は、出産予定日をもとに日程が計算されます。
※多胎妊娠とは、双子以上を妊娠している場合のことです。
産休育休の手当に関する計算はこちら 産休育休手当計算ツール
本ツールの計算結果は厚生労働省の定める産休・育児休業の各制度の定める期間に則り算出されています。 入力された出産予定日と出産日が離れすぎているなどの場合は、適切な結果が出ない場合があります。最終的な産休育休日程はかかりつけの医療機関および 所属する企業のルールにのっとり算出されてください。
産前休暇について
産前休暇は、出産予定日を含む6週間の取得が可能と定められています。
多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間取得可能です。
出産日が出産予定日より前倒しになった場合
出産が予定日より早くなった場合、産前休暇開始日は変わりませんが、産前休暇の終了日は早まった出産日までとなります。
出産日が出産予定日より遅れた場合
出産が予定日より遅れた場合、産前休暇開始日は変わりません。また産前休暇の終了日は出産日当日まで延長されます。
産後休暇について
産後休暇は、出産翌日から8週間の取得が義務付けられています。
ただし本人の希望と医師の許可がある場合は、出産翌日から最短6週間後に職場に復帰することができます。
出産日が出産予定日より前倒しになった場合
産後休暇も前倒しとなり出産日の翌日から産後休暇が始まります。産後休暇終了日もあわせて早まります。
出産日が出産予定日より遅れた場合
出産が予定日より遅れた場合、産後休暇の開始日や終了日も遅くなります。
産後パパ育休について
産後パパ育休(出生時育児休業)は、出産予定日を含めて8週間以内の期間で、合計4週間まで休暇を取得することができます。
この休暇は1回または2回に分けて取得することも可能で、家庭の状況に合わせて柔軟に使うことができます。
通常の育休と異なるのは、労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲内で休業中に就業することが可能という点です。
出産日が出産予定日より前倒しになった場合
実際の出産日から、もともとの出産予定日の8週間後までの期間の中で、合計4週間の休暇を取得することができます。
出産日が出産予定日より遅れた場合
出産予定日から、実際の出産日の8週間後までの期間の中で、合計4週間の休暇を取得することができます。
育休について
通常の育児休暇は、出産予定日から子が1歳になる前日まで取得することが可能です。
この休暇は1回または2回に分けて取得することも可能で、家庭の状況に合わせて柔軟に使うことができます。
出産日が出産予定日より前倒しになった場合
出産予定日から休暇を取得する予定だった場合は、休業開始日を前倒しして取得することができます。この際は期間変更手続きが必要です。
出産日が出産予定日より遅れた場合
出産が予定より遅れた場合でも、もともとの出産予定日育休をとることができます。
パパママ育休プラスについて
パパママ育休プラスは、通常の育児休業に加えて、子どもが1歳になる前後に取得できる延長育休制度です。
この制度を利用すると、子どもが1歳になる前日までの通常育休に加え、最大2か月まで休暇を延長することができます。
パパママ育休プラスの主な条件は以下の通りです。
- 夫婦ともに育児休業を取得すること: 父親と母親がどちらも育児休業を取得する必要があります。
- 子どもの年齢: 子どもが1歳に達するまでに育児休業を開始していること。
- 延長期間: 育児休業の取得可能期間を、子どもが1歳2か月になるまで延長できます。
- 休業期間の制限: 育児休業の対象となる期間(パパママ育休プラスの期間を含む)は、夫婦それぞれが合計1年間までです。
- 「本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日であること」という条件があるため、 先に育児休業を取得した人は、パパママプラスを申請することはできません。育休を同時に開始した場合は、夫婦のどちらが、 もしくは、夫か妻のどちらか一方の育休を遅く開始したほうにパパママ育休プラスを申請する条件が当てはまります。
育休の延長について
通常の育児休暇は、通常子が1歳になる前日まで取得可能ですが、あずけられる保育園が見つからないなど、やむなく家庭で保育を継続せざるを得ない状況の場合 1歳6か月から、最大2歳まで育休期間を延長することができます。